ペルオキシソームの新しい機能を発見! (筆頭著者による論文紹介)
今回、筆頭著者による論文紹介、ということで、東大薬の田中秀明さんにご寄稿いただきました!
比較的マイナーなオルガネラ、ペルオキシソームの新しい機能を発見したという報告です。とても丁寧に書いていただきました!ぜひ最後までご覧ください!
-----
ペルオキシソームの新しい機能を発見!-ミトコンドリアの動態・細胞死経路の制御-
皆様、ペルオキシソームというオルガネラをご存じでしょうか?
ペルオキシソームはほぼすべての細胞がもつ脂質一重膜で覆われたオルガネラであり、主に脂肪酸の酸化や活性酸素の除去といった細胞の代謝機能を担うことが知られています。
細胞内において、ペルオキシン遺伝子群によって形成されています。ペルオキシン遺伝子群が欠損することで、ペルオキシソームの機能不全が引き起こされます。ヒトにおいて、ペルオキシン遺伝子の欠損は、ツェルベーガー症候群をはじめとする非常に重篤な疾患の原因となります。ツェルベーガー症候群の患者は筋緊張低下、顔面形成異常、神経遅滞など多臓器にわたる影響が表れ、重篤な場合では出生後一年以内に死亡してしまいます。
このことから、ペルオキシソームが生体内で重要な役割を果たしていることは明らかです。しかしながら、ペルオキシソームの機能解析はあまり進んでいません。恐らく読者の方も、「教科書で見た気がするけど、あまり覚えてないな」くらいの認識ではないでしょうか?
私は、この重要だけれど謎の多いオルガネラ、ペルオキシソームに注目し、その機能解析を行うことにしました。はじめは何に注目すればいいかわからず、暗中模索の時期もありましたが、最終的にミトコンドリアとの新たな相互作用を見出し、論文としてまとめることができました。ここでは、代表的な結果を紹介しつつ、どのように自分の研究が進んでいったかをまとめてみたいと思います。参考にしていただければ幸いです。
---
ペルオキシソームの機能を探索すべく、まずペルオキシソーム形成に必須の遺伝子Pex3をCRISPR-Cas9システムでKOし、ペルオキシソーム欠損細胞を樹立しました。免疫細胞染色を行うと、実際この細胞ではペルオキシソームが完全に消失していることが観察されました。
ここで、とりあえずほかにもいろいろなオルガネラを染色してみよう、ということになり、小胞体、ゴルジ体、ミトコンドリアなど様々なオルガネラを観察してみました。色々と面白いことが分かったのですが、一番大きな表現型が「Pex3のノックアウトによってミトコンドリアが顕著に断片化している」というものでした。この現象は面白い!と思い、ペルオキシソームによるミトコンドリア動態への影響についてさらに調べることにしました。
ペルオキシソームが本当にミトコンドリアの動態制御にかかわるのか?ということをさらに調べるため、ペルオキシソームの十分性について検討することにしました。ここで用いたのが、4-PBA(4-フェニル酪酸)です。これは、PPARシグナルとPex11の経路を介してペルオキシソームを増加させる薬剤です。これを細胞に添加すると、実際にペルオキシソームが増加することが観察されました。この時、ミトコンドリアの形態はどうなっているかというと、驚くべきことに4-PBAによりミトコンドリアが顕著に伸長する像が観察されました。この4-PBAによるミトコンドリアの伸長が本当にペルオキシソームを介しているかを調べるため、同じ実験をペルオキシソーム欠損細胞で行うと、通常細胞で見られたミトコンドリアの伸長は観察されませんでした。このことから、4-PBAはペルオキシソームを増加させることでミトコンドリアを伸長させていることが示唆されました。

ここまでの結果から、ペルオキシソームの新たな機能としてミトコンドリアの動態を伸長方向へと制御していることが分かりました。次に私は、
②ペルオキシソームがミトコンドリアを制御する生物学的意義
について検証することにしました。
①: ペルオキシソームはどのようにミトコンドリア動態を制御しているのでしょうか?そこで注目したのは、ミトコンドリアの分裂を主に担う分子、Drp1です。この分子はミトコンドリアだけでなくペルオキシソームの分裂にも寄与していて、実際ペルオキシソームにもDrp1は局在することが知られています。そこで、
「ペルオキシソームはDrp1の制御を介してミトコンドリアの局在を調節する」という仮説を考え、検証することにしました。はじめにDrp1の局在を観察すると、ペルオキシソーム欠損細胞でミトコンドリア上のDrp1が増加していることが明らかになりました。さらに、このDrp1がペルオキシソーム欠損細胞におけるミトコンドリア断片化を起こしているのかを検証するためにDrp1のKDを行うと、ペルオキシソーム欠損細胞におけるミトコンドリア断片化は顕著に抑制されました。以上の結果より、ペルオキシソームはDrp1の局在制御を介してミトコンドリアの形態を制御することが分かりました。
②ペルオキシソームがミトコンドリアの形態を制御する意義について、ペルオキシソームが欠損するとミトコンドリアが断片化することは先述しました。ミトコンドリアの断片化は膜間腔タンパク質シトクロムCの細胞質放出、並びにアポトーシス経路のカスパーゼ活性化にかかわります。そこでシトクロムCを観察すると、驚いたことにペルオキシソーム欠損細胞では通常ミトコンドリアにいるシトクロムC が細胞質に拡散していました。さらにこのとき、実行型カスパーゼの活性化も起こっていることも明らかになりました。すなわち、ペルオキシソームが欠損することで細胞死誘導経路が活性化していることが分かりました。では、その下流のアポトーシスは起こっているのでしょうか?
AnnexinV binding assayによって細胞のアポトーシスを検出すると、想定とは異なり、ペルオキシソーム欠損細胞ではアポトーシスはほとんど起きていませんでした。すなわち、ペルオキシソームの欠損によりシトクロムCの拡散・カスパーゼの活性化は起こるものの、アポトーシスを起こすには不十分であることが示唆されました。
では、この細胞死を起こさないsub-apoptoticなカスパーゼの活性化を抑制することにはどういった意味があるのでしょうか?私は、細胞のストレス感受性に注目しました。
我々の細胞は日々様々なストレス(酸化ストレス、小胞体ストレス、DNAダメージ、etc…)にさらされています。ストレスがかかった細胞は、まずそのストレスを解消するための経路を活性化させます。しかし、ストレスがかかり続けたり、過剰なストレスがかかったりした場合は、細胞はアポトーシスを選択します。私は、ペルオキシソームがミトコンドリアを介したストレスによるアポトーシスを調節している可能性を考えました。そのため、ペルオキシソーム欠損細胞にDNAダメージを添加し、アポトーシスを検出すると、通常細胞に比較してアポトーシスする細胞の割合が顕著に増加しました。このことから、ペルオキシソームによるカスパーゼ活性化調節は、細胞のストレス感受性にかかわることが示唆されました。
全体をまとめると、私は本論文においてペルオキシソームがDrp1の局在を介してミトコンドリアの動態を伸長方向へと制御している、という新たな機能を見出しました。この機能の破綻はミトコンドリアの断片化、シトクロムCの拡散、細胞死経路の活性化を引き起こすことも見出しました。

ミトコンドリアの形態は、様々な生命現象にかかわっています。先述のアポトーシスはもちろん、神経幹細胞の分化や、ニューロンの軸索におけるミトコンドリアの適切な配置にもミトコンドリア動態は重要です。本研究でミトコンドリア動態をペルオキシソームが制御することが明らかになったことにより、ペルオキシソームもまたそういった生命現象にかかわりうることが分かり、よりペルオキシソームの重要性が強調されたかと考えています。
さらに、本研究で見出したペルオキシソームによるミトコンドリアの形態制御の破綻が、先述のツェルベーガー症候群(ペルオキシソーム欠損症候群)の発症にかかわっている可能性もあります。特に、ミトコンドリア動態やカスパーゼの異常活性化は神経変性疾患にかかわるので、ツェルベーガー症候群における神経変性疾患様の症状にミトコンドリア動態制御破綻が関与する可能性を現在検証しています。
結果を丁寧に説明してきましたが、結局のところ私が読者の皆様に覚えておいていただきたいポイントは、「ペルオキシソームって結構大事なオルガネラなんだな」ということです。この機会にぜひ覚えておいてください!
発表論文
Peroxisomes control mitochondrial dynamics and the mitochondrion-dependent pathway of apoptosis, Journal of Cell Science, 2019
------
バイオステーションでは、筆頭著者の方による論文紹介を募集しています。どのような分量でも構いませんので、ぜひご寄稿いただけると幸いです。
詳細につきましては、以下のリンクもご覧ください
今後ともバイオステーションをよろしくお願いいたします。
神経前駆細胞の大移動@がん

哺乳類の繁栄を支える遺伝子

精子のpHセンサー

細胞核構造のダイナミックな変化が学習に大事!

ATAC-seqの歴史
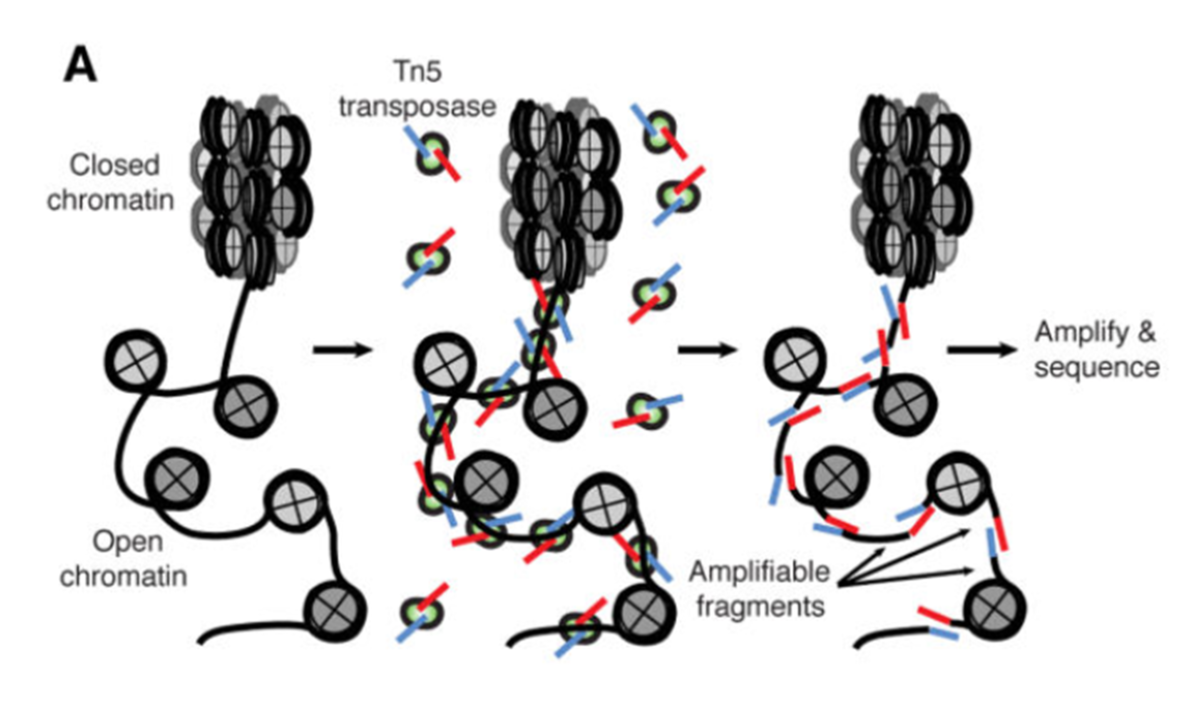
ヒストンの持つ驚きの機能_2
